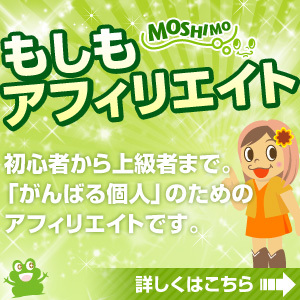本を紹介するリンクの作り方は?
紹介するコツや注意点は?
ブログで本を紹介するリンクを貼るのは簡単です。以下のようなリンクを貼ってみましょう。
このリンク広告はもしもアフィリエイトで作りました。もしもアフィリエイトの「かんたんリンク」という機能を使えば簡単です。
著作権にも注意しつつ本を紹介しましょう。
著作権の注意点
①:要約はOK
②:内容の丸写しはNG
③:表紙画像はNG
④:引用はOK
本を紹介するなら、最低限の著作権は理解しておきましょう。著作権を理解して置けば安心して紹介できますよ。
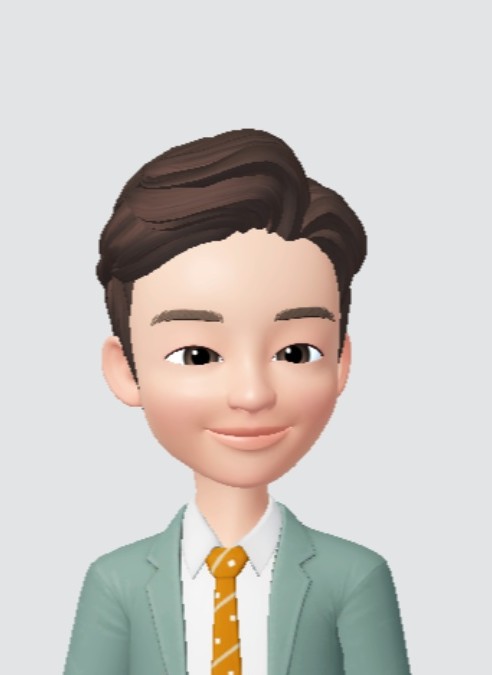
副業ブログで収益6桁を積み上げてきました。
本を紹介して稼ぐのもありですね。
この記事を読んでいただければ、ブログで本を紹介して収益化する方法が」分かりますよ。
-

-
もしもアフィリエイト「かんたんリンク」の貼り方
もしもアフィリエイトの「かんたんリンク」を使うと、以下のような広告が簡単に作れます。 かんたんリンクの作り方は、以下の3ステップだけです。 画像付きで詳しく解説していきます。 最後まで読んでいただけれ ...
続きを見る
本の紹介リンクを貼る方法
ブログに本を紹介するリンクを貼れば収益化できます。
一番簡単な方法は、もしもアフィリエイトを使う方法です。
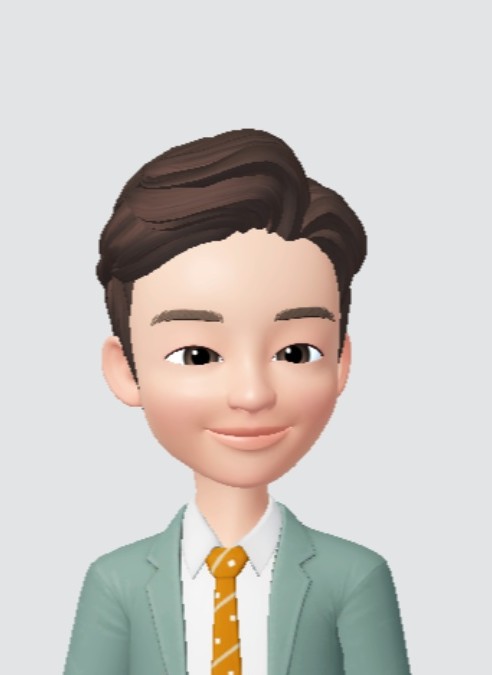
もしもアフィリエイト
もしもアフィリエイトを使えば以下のようなリンクも簡単です。
まずは、もしもアフィリエイトに登録しましょう。
\\詳しくはこちら//
※無料登録は簡単5分です
[PR]
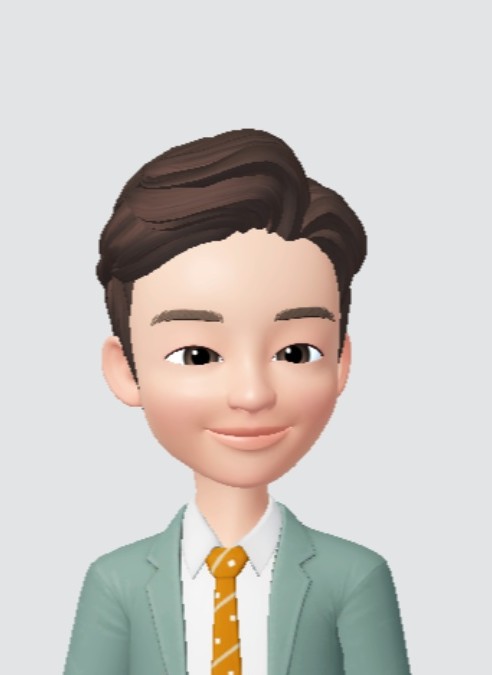

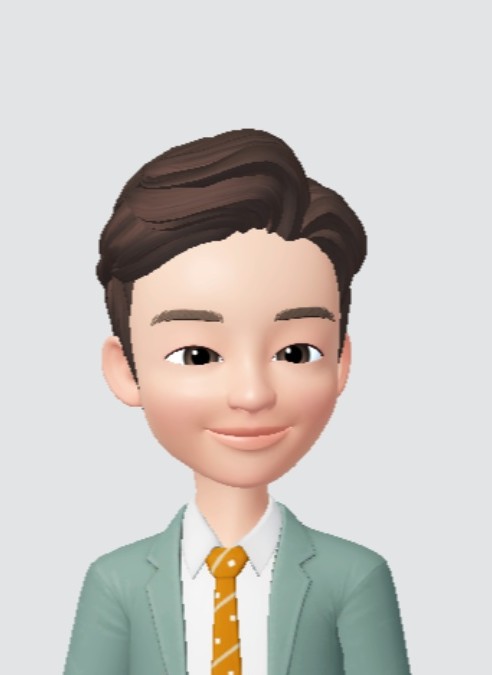
かんたんリンク.png)
もっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
-

-
もしもアフィリエイト「かんたんリンク」の貼り方
もしもアフィリエイトの「かんたんリンク」を使うと、以下のような広告が簡単に作れます。 かんたんリンクの作り方は、以下の3ステップだけです。 画像付きで詳しく解説していきます。 最後まで読んでいただけれ ...
続きを見る
【紹介の仕方】本を読んだあとの未来を語ろう
広告の貼り方が分かったら、本を紹介していきましょう。
紹介のコツは、「本を読んだあとの未来を語ること」です。つまり、マーケティングでいう”ベネフィット”です。
「本のここが良かった」だけじゃダメなんです。「本のここが良かったので、こんな風に役に立った」という感じです。
本を読んだあとの未来を語ろう
✖この本の解説が分かりやすかった。
◎この本の解説が分かりやすかったので、僕の文章力が向上しました。
単に本の要約をするのではなく、本を読んだ結果どんな良いことがあったかを語るのがポイントです。
本の紹介リンクで収益化できる
本の紹介で収益を稼いでみましょう。
「本のリンクを貼る→本を読んだあとの未来を語る」の流れで収益化できます。
報酬率は以下の通り。
- Amazonアソシエイト:2%
- 楽天:2%
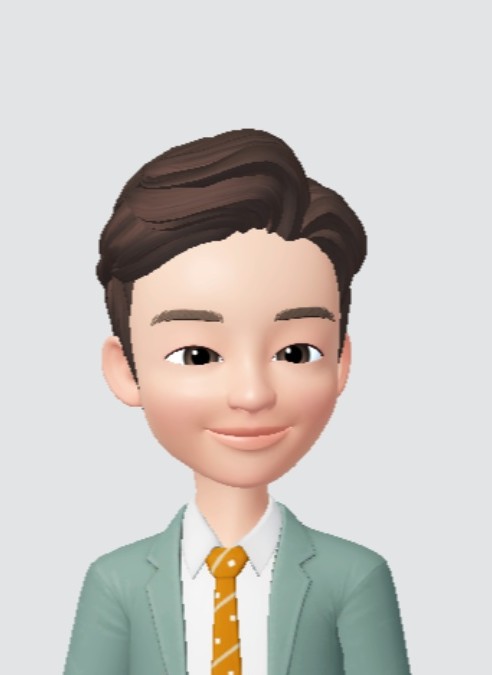
報酬は決して高くないので、収益を伸ばしていくには積み上げていくしかないですね。
著作権に注意しつつ紹介しよう
ブログで本を紹介するなら、著作権についての理解が必須です。
ポイントは以下の通り。
著作権の注意点
①:要約はOK
②:内容の丸写しはNG
③:表紙画像はNG
④:引用はOK
簡単に言うと、要約や引用はOKです。文書の丸写しや、表紙画像の利用はNGです。
①:要約はOK
本の内容の要約はOKです。なぜなら、本の内容には著作権が引っかからないからです。
細かい話になりますが、本の”表現”に著作権がかかりますが、内容の”アイデア”には著作権がかかりません。
文化庁のサイトには、著作物について以下の解説があります。
著作権は表現の保護であり、アイデイアは保護しません。一般に学説は、このアイデイアに相当するものと考えられていますので、著作権法の保護はありません。なお、学術論文自体は著作物であり、例えば論文の無断コピーが一般に著作権侵害になるのは言うまでもありません。
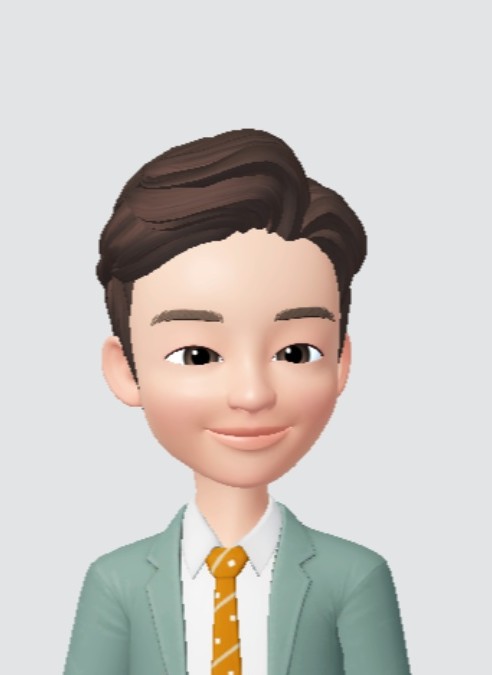
分かりやすく本を要約して紹介してみましょう。
②:内容の丸写しはNG
内容の丸写しはNGです。なぜなら、本の表現を使うことになるからです。
著作物の定義には、「表現したもの」と書かれていましたね。以下の通りです。
著作権は表現の保護であり、アイデイアは保護しません。
つまり、要約はOKだけど丸写しはダメです。
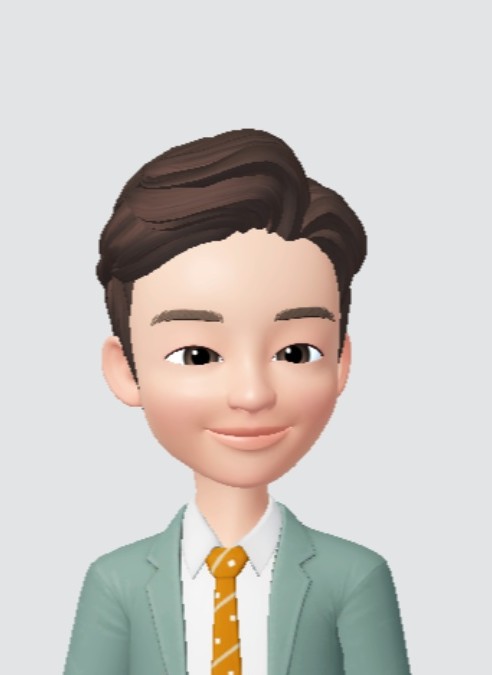
そもそも、本を紹介して購入を促したいので、丸写ししても良いことは一つもないですね。
③:表紙画像はNG
本の表紙のデザインにも著作権があるので要注意です。
本の表紙画像を使用するのはやめましょう。特に、アイドルなどが表紙になっていたら絶対アウトです。

画像を使いたい場合は、広告リンクを貼り付けましょう。もしもアフィリエイトなどで作った広告なら問題ないです。
例えば、以下はマンガ「宇宙兄弟」の広告リンクです。クリックするとAmazonの商品ページに飛びます。
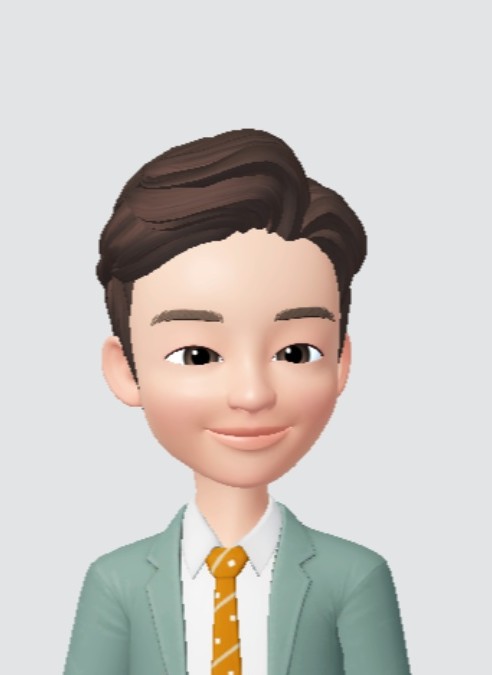
上記の画像リンクは、もしもアフィリエイトの「どこでもリンク」で作れます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
-

-
もしもアフィリエイト「どこでもリンク」の貼り方
もしもアフィリエイトのどこでもリンクを使うと、任意のページへのリンク広告を作れます。 例えば、Amazonの検索結果のページのへのリンクを広告にできます。 以下のリンクが、どこでもリンクになっています ...
続きを見る
あるいは、まれですが著者のtweetを埋め込むのもOKです。
#宇宙兄弟FFS本 第2弾が発売🚀
今度のテーマは"自己分析"🔎
あなたの強みは『#宇宙兄弟』のどのキャラと似ていて、その強みを相手に理解してもらうためにはどのように表現すればよいのか🤔
キャラクターとストーリーでわかりやすく解説!11/3(水)発売!ご予約はこちら👇https://t.co/EvzXK5JA0N pic.twitter.com/Cjy0YraIxs
— 宇宙兄弟 40巻発売中🚀 (@uchu_kyodai) November 1, 2021
表紙画像を使いたいときは、広告リンクか著者のtweetを使いましょう。
④:引用はOK
本の引用は常識的な範囲ならOKです。著作権法でも、引用は許可されていますよ。
「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。
この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(パロディ写真事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって実務的な判断基準が示されています。
例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。
なお、近年の判例では、これらの判断基準によらず、引用する目的、引用の方法・態様、著作権者に及ぼす影響の程度等を総合的に考慮した上で判断しているものもあります。
つまり、常識的な範囲で引用してOKということです。「公正な慣行に合致すること」とか「正当な範囲内」と書いてありますね。
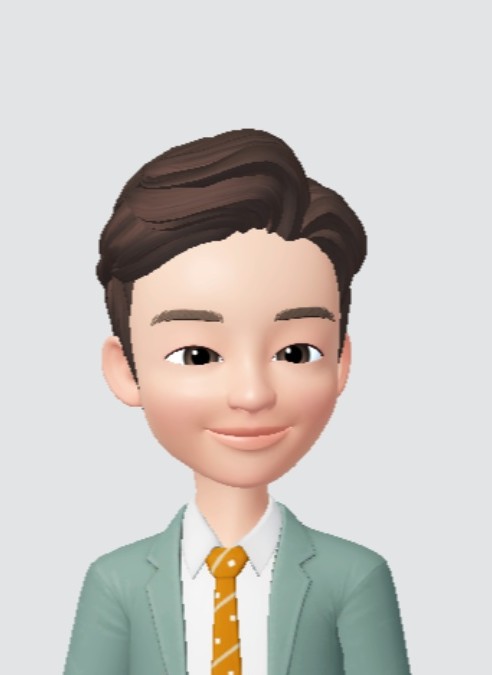
むしろ、きちんとした引用なら宣伝にもなるし、本の評価も上がるので有益ですよね。
ただし、引用のルールを守る必要があります。
4つの引用ルールがあるので、以下に解説していきます。
ブログに本の内容を引用するときはルールを守りましょう
引用ルールは以下の4つ
✔️引用する必然性があること。
✔️かぎ括弧などで引用部分を区別。
✔️ブログとの主従関係を明確にする。
✔️出所を明示する。作者への敬意を抱きつつ引用しましょう😊
3つの引用ルールを守ろう
ブログで本の引用をするのはOKですが、ルールを守る必要があります。
文化庁の解説をまとめると以下の3つのルールを守る必要があります。
[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのか
上記の通り、3つの引用ルールが明記されています。
まとめると以下の通り。
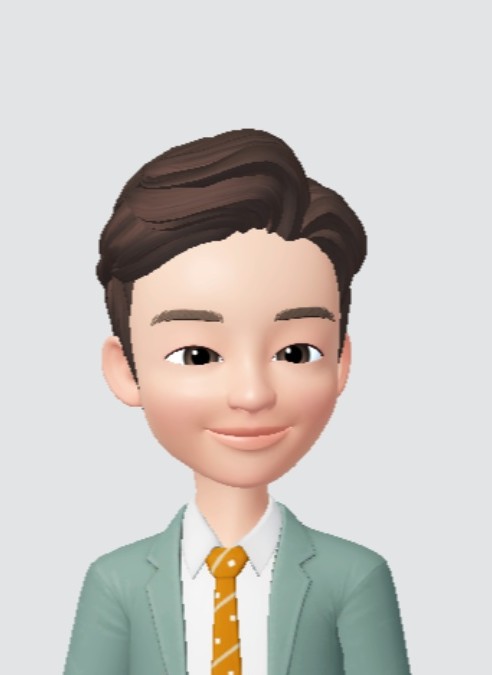
以下に3つの引用ルールを解説していきます。特に、ブログにどう当てはまるか解説します。
引用ルール①: 主従関係
自分の記事と引用物の主従関係を明確にしましょう。これが引用ルールの1つ目です。
[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
つまり、自分の主張をした上で引用です。メインは自分の記事ということ。
引用だけで成り立っているような記事はダメです。
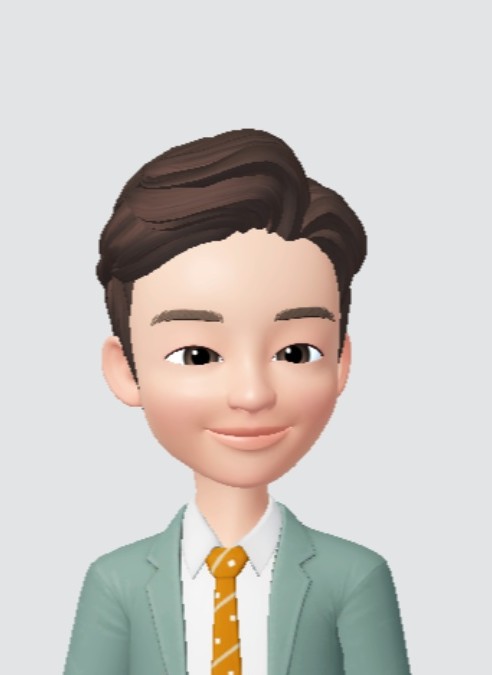
本を紹介する書評記事なら、自分の感想がメインになるように書いていきましょう。
主従関係を意識しよう
✖この本にはこう書いてあります。「引用~」つまりこういうことです。「引用」
◎僕はこの本で文章スキルが上がりました。例えば、「引用~」
上記の通り、引用がメインはダメです。
むしろ、自分の主張をした上で引用していきましょう。
引用ルール②: かぎ括弧
かぎ括弧を付けたりして、引用であることが分かるようにします。これが引用ルールの2つ目。
[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
ブログの場合は、以下のようなタグをつかえばOKです。
引用引用引用引用引用
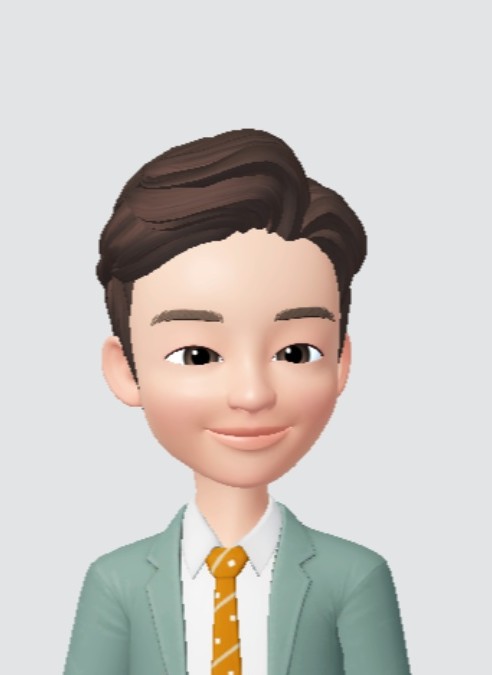
きちんと引用であることが分かるようにしましょう。
引用ルール③: 引用する必然性
引用することに必然性があることが必要です。これが引用ルールの3つ目です。
[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのか
基本的に、ブログなどで紹介するときに引用することには必然性がありますね。「この本が良かった」と言いながら、全く引用しない方が不自然です。
著作権を守りつつ本を紹介していこう
繰り返しますが、著者への敬意を持ちつつ紹介するのが大事です。
著作権は、何が何でも作品を保護するものではありません。むしろ、上手に紹介して、作品を世に広めるように意図されています。
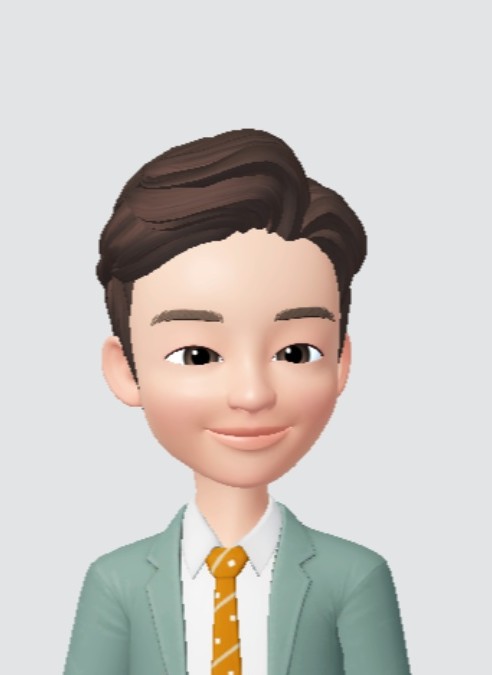
本の売り上げが伸びれば、著者が喜ぶのも当然。
あなたも、ブログで上手に本を紹介して見てください。
まとめ
本を紹介するリンクは、もしもアフィリエイトなどを利用して作成しましょう。
もしもアフィリエイトの「かんたんリンク」で以下のような広告を作れます。
Amazonオーディブルも、もしもアフィリエイトを使えば簡単に紹介できますよ。
著作権に注意しつつ紹介しよう
著作権に注意しつつ、本を紹介していきましょう。
以下の4つのポイントに注意しつつ記事を書いていきましょう。
著作権の注意点
①:要約はOK
②:内容の丸写しはNG
③:表紙画像はNG
④:引用はOK